report
2023.02.07
Vol.18『観光ビッグデータとプラットフォーム学』
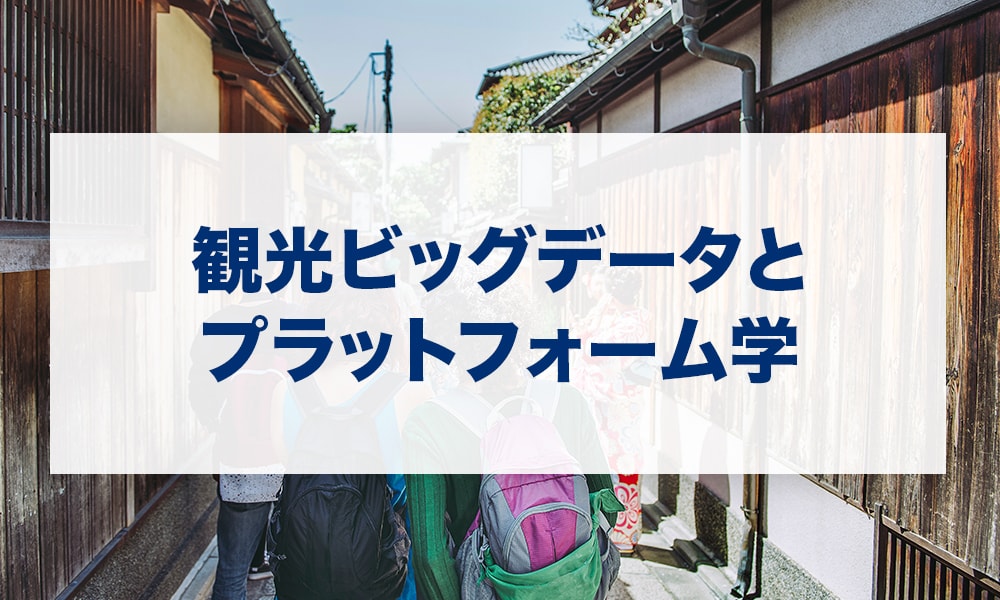
2023年2月7日にオンラインで開催された「プラットフォーム学連続セミナーVol.18『観光ビッグデータとプラットフォーム学 〜持続可能な観光業や地方創生にデジタルツーリズムが不可欠な理由〜』」。株式会社JTBの北邨昌子氏、一般社団法人メタ観光推進機構 理事/エリアLOVEWalker総編集長の玉置泰紀氏が登壇し、コロナ禍による低迷から復活しつつある観光業におけるプラットフォームは何か、デジタル化による発展等について、情報提供とディスカッションが行われました。進行役は京都大学 プラットフォーム学卓越大学院 プログラムコーディネーターの原田博司教授が務めています。
●DXで観光地が持つ課題解決を多面的に解決していく
観光に関する登壇者それぞれの取り組みとして、まずJTB北邨氏が自社のエリアソリューション事業を紹介しました。この事業はこれまで旅行エージェントに対してサプライヤーの関係だった旅館などの観光事業者を顧客と位置付けてビジネス展開するもので、観光地のDXや人材・インフラなどの課題解決を図り、地域の活性化を目指しています。北邨氏はその事業事例を3点紹介。一つ目は熊本県阿蘇郡小国町の絶景スポット鍋ヶ滝での「観光地デジタル化支援事業」。鍋ケ滝はそれまでは訪れる人の少ない知る人ぞ知る場所でしたが、CMに採用されたことをきっかけに観光客が急増。車でしかアクセスできないため大渋滞が発生し、いわゆる観光公害が生じている状態になりました。そこにJTBの日時指定機能を持つ入場管理システムを導入。旅行者の利便性の向上と地域住民の生活環境の保護に貢献したことで、2022年度世界のサステナブル観光地100選に選出されました。二つ目の事例はホテルや旅館などの宿泊施設に対して業務効率化の支援を行う「観光地整備・運営支援事業」。宿泊者から直接評価されない業務をデジタル化することで、人でしかできないコミュニケーションなどの時間を増やし、宿泊者の体験価値向上を目指しています。ここではチェックイン・アウトをはじめとする旅館業の各業務と管理システムを繋げるハブシステムを開発し、情報の一元管理・処理の省力化を可能にしました。三つ目は旅の目的そのものを生み出す「タビナカコンテンツ提供事業」。これは新しい観光コンテンツの開発や、既存のコンテンツをパスで繋ぐことでさらなる人流を促す取り組みです。また、デジタル化によって観光客の周遊行動を補足することで、より魅力のある観光地づくりを目指しています。
続いてメタ観光推進機構の玉置氏が「CGM(Consumer Generated Media)から生まれてシビック・プライドを醸成する新しい観光(観光DX)」について解説を行いました。玉置氏は「メタ観光」について、従来型の名所旧跡観光に加えて、映画やドラマのような創造された情報を観光に取り入れた「観光についての観光」であると説明。ただしいわゆる聖地巡礼が従来の観光と切り離されているわけではなく、同時に多層的に存在すると解説します。このメタ観光を劇的に進めたのがGoogleマップ。歴史や名産品、地学などをすべて同じ皿の上に乗せられるようになり、ここにゲームの要素を加えるとポケモンGOに、地形や地学、鉱物学まで取り込めば『ブラタモリ』になると述べました。デジタル(ウェブ、アプリ、SNSなど)+アナログ(パンフレット、雑誌など)+リアル(イベント、フェスなど)+位置情報(映画、アニメ、歴史、地学など)=マルチにコンテンツとレイヤーを統合して、コミュニティを形成・継続するのがメタ観光で、本来出会わないものが重なる刺激がその魅力だと語りました。2020年に設立されたメタ観光推進機構では、文化庁のプロポーザルに選出され「すみだメタ観光祭」を開催。マップやデータベースなどのメタ観光開発をもとに、キュレーション地図やアプリの作成、ガイドツアーの実施などメタ観光振興を行いました。さらに既存のレイヤーだけではなく、アーティストによる墨田区を題材にした作品制作や暗渠愛好家によるガイドツアーなどの新規レイヤーの作成も推進しました。最後にメタ観光を実装化する観光DXのトライアングルとして、コンテンツ(記事、雑誌、YouTubeなど)、メディア(エリアLOVEWalker、SNS、オウンドメディアなど)、リサーチ(Twitterトレンド解析、都市指標、POSデータなど)を挙げ、観光DXは様々なものを多層的に繋いで展開していくのが重要だとまとめました。
●細分化・多様化する観光ニーズへ応えるために何故デジタル化が必要なのか
後半のディスカッションパートはまず原田教授の「なぜ観光のデジタル化をするのか」という問いからスタート。北邨氏は労働集約型である観光業を日本の主力産業にするためにはデジタル化による業務効率化は必須だと回答。コロナ禍による影響を問われると、コロナ禍を経て観光客の取り合いになったとき、情報を的確に届けるためデジタルマーケティングがさらに重要になった点、一旦観光業から離れた人たちと戻ってくる観光客のギャップを埋めるためにデジタルが不可欠である点を挙げました。また、リアル旅行に行けない人に観光地の魅力を伝える手段としてオンラインツアーやバーチャル観光が生まれたが、現状ではリアルに誘導するためのコンテンツであり将来的にはそれ自体でマネタイズできるようになるのかもしれない、と展望を語りました。
『東京ウォーカー』に携わった玉置氏は、今のような雑誌が生まれた契機が1970年の日本万国博覧会(Expo '70)に合わせて実施された電通と国鉄(現JR)の一大キャンペーンにあると述べました。これにより情報を提供することがビジネスとして一般化し、1970年に『anan』、1971年に『non-no』、都市情報誌の先駆け『プレイガイドジャーナル』が刊行されるなど、今の雑誌に繋がる流れのスタートがExpo '70だと持論を展開しました。1970~80年代はまだそれほど大きな影響を持っていなかった情報誌でしたが、バブルがはじけて不況の時代が訪れると効率よく情報を入手することが重要視されるようになり、1990年に創刊された『東京ウォーカー』は、テレビ番組雑誌『ザ・テレビジョン』と街情報誌『Hanako』、エンタメ情報誌『ぴあ』を足して割ったような雑誌として、情報を効率よく収集するのに最適だとして、1990年代が最も売れた期間となりました。この『東京ウォーカー』の発明とも言えるのが2×2センチほどのミニマップ。それまでの雑誌にはなかった小さい地図をお店の情報と合わせてデータボックスにすることで、スポットの情報が簡単に得られるようになり、デジタル化した現在にもこの様式は受け継がれていると語りました。
情報収集の効率化を求めるユーザー側の傾向について問われた北邨氏は「細分化・多様化が広がってきている」と説明。その理由を企業側が出した情報をユーザーが選択する形式から、そのユーザーに最適な情報を届ける・用意する形式へ変わってきており、自分好みの情報の取捨選択ができるようになったからだと分析。場所へのタグが増えるのと同様に、「ビールが好き」「このアニメのファン」「母親である」といったように個人が持つタグも増えてきており、タグとタグを結び付ける仕組みづくりが重要だと語りました。ユーザーが求める情報の変遷について玉置氏は、名所旧跡といった従来型の観光に風穴を開けたのが、アニメやドラマと観光を結び付けるコンテンツツーリズムだと説明。さらに最近は災害被災跡地、戦争跡地など人類の死や悲しみを対象にしたダークツーリズムや、文化遺産や自然遺産を観光資源とするヘリテージツーリズムなど多様化している現状に対して、メディアや観光業者がそれを求めるユーザーに届けるのが重要だと語りました。
一つの場所に複数のタグを付与してメタ情報にするにはフォーマットが必要なのではないかという原田教授の問いに玉置氏は、「すみだメタ観光祭」の事例で60以上のレイヤーと1700以上のタグを作成したが「情報過多になってしまった」と説明。それを解決するために情報を切り出すキュレーターが必要になると考えてキュレーターによるツアーなどを実施し、そこで得た学びとして10~20程度のレイヤーと、100~200程度のタグが適当であるということ、そして現状はフォーマットを作ってパターン化はあえてしないほうが楽しいのではないかと考えていると語りました。また、無名な地域こそメタ観光が活きる可能性があり、かつてそこに何かが起きた、地形や区割りには何か理由がある、そういったことを掘り返してその土地の魅力を再認識して好きになる「シビック・プライド」を通じて地域が活性化する、というのがメタ観光推進機構の将来像だと解説しました。
観光業のDX化における技術的な側面での取り組みや課題について、玉置氏は人流分析とSNS分析を組み合わせた「都市指標」を作ろうとしていると紹介。どの曜日のどの時間帯にどう人が流れているのかという人流データに膨大なSNSの投稿データを組み合わせることで、どの人がどういった感情で動いているのかを街(駅)単位で計測する「エリアクオリア指標」を開発したことを挙げ、こういった組み合わせにより可能性が拡がると述べました。北邨氏はカーナビの移動情報と観光情報を組み合わせて新たなデータが取れないか取り組んでいると説明。カーナビに観光情報をプッシュ通知して実際にそこに行ったのかというデータを実験的に取得しており、目的地への動機づけを増やすことで観光の需要喚起に繋げていきたいと語りました。また、そのためには集約したデータを解釈して次の施策に繋げていくサイクルが重要であり、技術の発展と共に人材も育成していかなければならないと述べました。玉置氏はこの人材育成のヒントはキュレーターやプロデューサー・ディレクターにあるのではないかと推測。優れたキュレーターの仕事から学ぶことで膨大なデータを活かせるのではないかと述べました。北邨氏は、JTBではその土地を深く理解した観光プロデューサーを各地にもっており、そこにデータを読み取る力を加えていきたいと語りました。
今後の展開・実現のために期待される技術や施策について北邨氏は、人材育成・外部人材の獲得のために、観光産業の魅力を高めて人材交流できるようにしていくのが大事だと語りました。玉置氏は、東京・西新宿には5Gや高速Wi-Fi、カメラやセンサーなどの多様な機能を搭載したスマートポールが約20本設置されていると紹介。このスマートポールはサイネージ用途以外に人流も見ることができるため、個人情報に配慮する必要はあるものの、こういった外部情報の取得技術の進化には余地があるとの意見を示しました。JTBなどの大企業やニッチなメタ観光を扱う中小あるいは個人業者は今後どのように展開するのか問われた玉置氏は、かつての日本は現在の中国のように、旅行は団体から個人へと移り変わるのが基本であると指摘。そこには富裕層をターゲットにした単価の上昇へ対応が必要となるものの、富裕層がお金を使って観光を楽しむというビジネスに日本はまだまだできておらず、これを実現できるのはJTBのような大手企業ではないかと述べました。これに対して北邨氏は、観光産業をサステナブルな産業として盛り上げていきたい、団体も個人も含めて総括的に扱えるのがJTBのような企業の強みなので、そこから得たデータを地域に還元して魅力を磨き上げるのが我々の役割だと語りました。