report
2023.03.01
Vol.19『デジタル防災とプラットフォーム学』
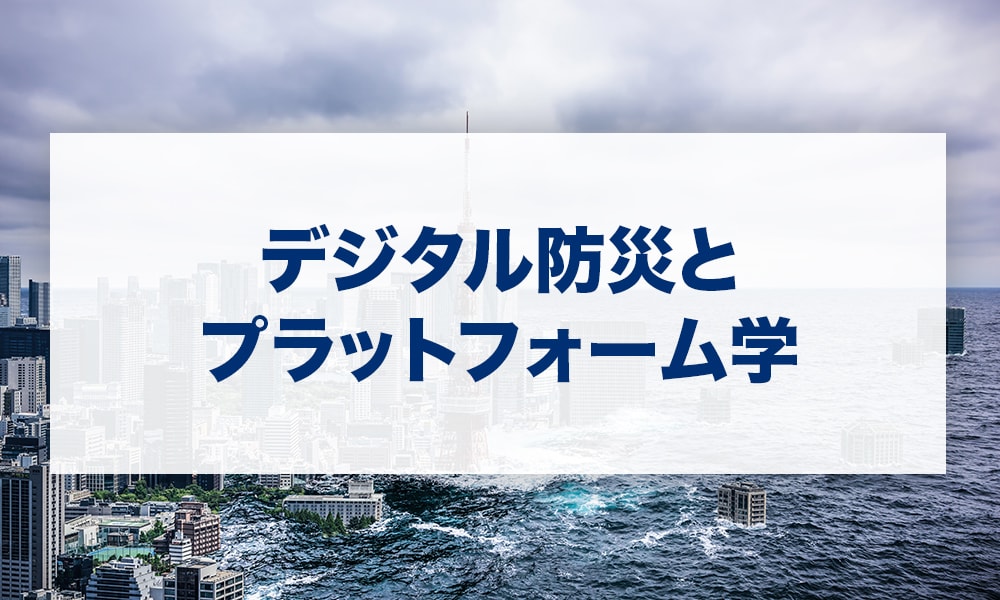
2023年3月1日に、「プラットフォーム学連続セミナーVol.19『デジタル防災とプラットフォーム学』〜減災・防災に貢献するデジタルツインやAI予測技術の最新事情〜」が開催されました。“情報学版リベラルアーツ”の創出を目指し、情報学と複数領域を連携させて新しい価値創造を目指すプラットフォーム学。そのプログラムの一環で開催している連続セミナーの第19回目です。
2023年は、関東大震災の発生した1923年から100年目となります。また、近年の災害を振り返ると、阪神淡路大震災(1995年)や東日本大震災(2011年)の発生、2020年の熊本地域を襲った豪雨など、自然災害の大規模化と広範囲化が感じられます。その中で、今後も発生し続けていくであろう災害時に被害を減らすべく、技術発展から仕組みづくりまで、そしていざ発災時に適切に活用できるような社会実装が重要となります。
セミナーには、東京海上日動火災保険株式会社dX推進部ビジネスデザイン室 課長の大島典子氏、Arithmer株式会社 先端技術事業部 浸水AI推進部 部長の勝又史郎氏が登壇しました。進行役は京都大学 プラットフォーム学卓越大学院 プログラムコーディネーターの原田博司教授です。
●損害保険会社が主導となって、設立したビジネス化することを目的とした防災コンソーシアム
大島氏は、「今年は関東大震災から100年目。現代で同じ地震が起きたら、被災状況は減らせるのでは?」という思いから、東京海上グループの減災・防災の取り組みとして2021年に設立したコンソーシアム「防災コンソーシアム CORE」を紹介しました。なぜ保険会社が防災に関するコンソーシアムを立ち上げたのかという疑問に対して、大島氏は「保険は何か起きたらお支払いをするものだが、何か起きるより何も起きないことの方が、よほどお客様には幸せなこと」だという考えから、防災を主題としたコンソーシアム設立に至ったそうです。
コンソーシアムが目指している姿としては「被災を半減し、安心を2倍にする」こと、そして最大の特徴はビジネス化を前提として進めていることです。活動の軸としては、官公庁と連携して強靭な社会構築を目指す「協調領域」と、参画法人同士による新たな価値創造を目指す「競争領域」があり、2023年2月時点で、93社が参画。7つの分科会が立ち上がり、実証実験にとどまらないビジネス化に向けた活動を進めていることなどが、大島氏から情報提供されました。
●Arithmerの浸水AIの開発にあたって
Arithmerの勝又氏からは、「数学で社会を解決する」をミッションとする同社の主軸ソリューションである浸水AI、風力AI、運転AIが紹介されました。
浸水AIへ力を入れている背景としては、近年の台風や大雨の発生頻度の増加や、損害保険支払費用について東日本大震災での約1.3兆円に対し2018年台風21号では1兆678億円に及んでいるなど、水害の激甚化傾向があるそうです。取り組みとしては、災害前と災害後それぞれの状況を意識されているとのこと。災害前においては、被害を減らすために、事前の浸水情報の把握や避難タイミングを通知するサービスを進めています。そして災害後においては、迅速な復旧のために、保険金の早期支払や羅災証明書発行支援など、被災状況を迅速に把握のできるサービスを提供されています。提供実績としては、福島県広野町での「浸水高事前予測」や、1平方キロメートルあたり数カ所実測するだけで実現できる三井住友海上火災保険向けの浸水高シミュレーションなどがあるそうです。浸水AIを活用する自治体の利点としては、「過去データをAIに学習させるだけで、浸水現象の専門的な知識は不要」、「超高速での再現が可能」、「実測データやリアルタイムデータを使って、最新の予測値を得られる」などが挙げられました。今後は、土木工事における降雨による遅延リスクの回避や、大規模施設の浸水対策に応用を広げていきたいということです。
●保険会社主導でのコンソーシアムについて
登壇者によるディスカッションでは、モデレーターの原田教授が、デジタル防災の定義から、現在に至る災害と防災の歴史を紹介。数々の災害を被り、復興を繰り返してきた中で、東日本大震災をきっかけに復興庁が設置や、基盤的防災情報流通ネットワーク(SIP4D)などのインフラ整備など、常に新しい防災施策が生まれてきたことを振り返りました。一方で、技術的な観点でこの十数年を振り返ると、ソフトウェア的にはビッグデータやディープラーニング、ハードウェア的にはインターネットやGPSの位置情報、IoT、ドローンなど急速に発展したものの、避難所の状況把握や支援物資の供給などに関しては、革新的に変わった印象は薄いと指摘。その中で「被災を半分にして、安心を2倍にする」ために、どのように具現化をすることが重要か、どのようなアクションを起こせるかという議論が展開されました。
その議論のなかで、いまの時期に損害保険会社が防災コンソーシアムを立ち上げた理由について、大島氏が改めて説明しました。まず、損害保険業界はそもそもリスクを扱っている業界であり、100年以上に及ぶリスクに関するデータを保有しているため、これらのデータを他企業と掛け合わせることで、新しい何かが生まれることを期待されています。そして、既存の多くのコンソーシアムが研究や実証実験を目的としているため、社会実装に向けて「ビジネス化」を掲げたコンソーシアムを立ち上げたと語りました。
●内閣府、保険会社、ベンチャー企業との座組
以前に内閣府(防災)に出向していた経験のある勝又氏は、2015年にビジネスに特化して各業界の企業が集まり課題解決をすることを目的とした日本防災産業会議の立ち上げの経験を紹介しつつ、当時は現在のようなIoTやAIのような技術があるわけではなく、だいぶ取り組み方が違っていたことを振り返りました。
そして、大島氏と同様「今のタイミングこそ、損害保険会社が防災に深く関わることには意味がある」とコメント。その理由として、多くの損害保険会社は創業して100年近くになり、過去から蓄積したリスク対策に関するノウハウを専門的かつ大量に蓄積しており、それがAIの発展によって深く分析できるようになったことを挙げました。そのうえで、近年の災害は頻度と規模が大きくなっており、保険金支払いのための調査作業などは人的対応では間に合わなくなっているため、積極的に新しい技術を活用し始めたことを指摘。実際にArithmerの技術を用いた三井住友海上の事例では、保険金支払にかかる作業が166分の1に縮小された実績が紹介されました。
このように過去のデータを蓄積しており、かつ、生活者の迅速な生活再建のサポートを主軸としている保険会社が、ベンチャー企業との協業によって新たな災害対策に取り組み出したことは、ディスカッションでは自然な流れだと捉えられました。
一方で、「日本はスタートアップ企業を活かしきれていないことが、GDPが伸びていない、賃金が30年間上がっていない要因の一部になっている。すなわち、新しい企業が育っていない」という日本のスタートアップ界隈の課題も取り上げられました。現状、海外でも通用するような優れた技術を持っているスタートアップ企業であっても、体力がないため海外に打って出るほどのリソースがありません。だからこそ、そういった下支えをしてくれる、あるいは促進してくれるような仕組みを政府に求めたいという意見が、登壇者から寄せられました。
●大手企業とベンチャー企業をつなぐ枠組みづくり
これらの話を受けて原田教授は、大手企業とベンチャー企業が協働しようとした場合、規模や考え方のギャップが大きいことがスムーズなプロジェクト推進の障壁であり、その間を仲介するような立ち位置として、まさにコンソーシアムのような形式に損害保険会社が入るモデルが良いと提案されました。
そして大島氏からは、企業が保険会社主導のコンソーシアムに入るベネフィットが語られました。「防災コンソーシアム CORE」を例にとると、同コンソーシアムには東京海上日動やNTTなど、全国に支店があって、各地の顧客にリーチできる企業が参加しています。このため、スタートアップ企業の尖った技術を、埋もれさせることなく全国の顧客に届けることを期待できます。それらの大手企業にとっても、自分たちだけではできない、足りないところ、例えば人流データがほしいと言った場合にコンソーシアム内の他企業とのマッチングが可能になります。そして、大島氏は大手企業とスタートアップ企業が対等な立場で会話できる空間を作りたかったと語りました。
たとえば、大手企業のセキュリティー・ポリシーの厳しさと、スタートアップ企業の良い意味でのゆるさは対局の関係にあります。その中で、大手企業とスタートアップ企業が一対一で向き合った関係となってしまうと、スタートアップが不利な状況に陥ってしまったり、知的財産の多くが大手企業に手に渡り、スタートアップ企業はベンダー扱いになってしまったりといったことが懸念されます。そこで、コンソーシアムという一対一ではない多数の会社が集まることで、少しでも対等な関係が作れるのではと期待されていました。
これらのディスカッションを受けて、原田教授は損害保険会社が間を取り持つことで、大手企業とベンチャー企業同士を繋ぐ新しいモデルが出来ているように感じたとコメント。保険会社は、ベンチャー企業の体力をある程度保証しつつ新しい活動に導き、かつ、大手企業に対してはベンチャー企業との連携により出てきそうなリスクをある程度、保険会社のノウハウでリスクをなくす、もしくは緩和させることができます。損害保険業界が、すべての人の何かしら思っている不安を保険というかたちで安心してもらっているのと同様に、誰もが一丸となって同じ方向を向くべき防災・減災領域においても、会社同士を繋ぎ、リライアブルでありかつ安心なコネクションが作られる期待を語りました。
Arithmerの勝又氏は、三井住友海上出身でもあることから、損害保険会社の取り組みの変遷を紹介しました。今までの損害保険会社は、損害があった場合に金銭的価値で補填することがメイン業務だったのが、いまはその補償の前後にも目を向ける必要が出てきたと言います。それは、事故が起こらないように何ができるか、事故が起こった後でも復旧のために何ができるか、そしてそこから新しいビジネスモデルを作ることになります。三井住友海上、既存の知識や先入観からは生まれない新しいビジネスモデル構築のため、ベンチャーキャピタルとしても活動しており、多くの出資先の中から最も保険と親和性の高いベンチャー企業に、自社の社員を出向させているとのこと。このような枠組みを作ることで、技術力はあるが営業力が脆弱なベンチャー企業に対して、大企業と付き合うノウハウや成約させるためのノウハウを伝えて支援しているそうです。間を繋ぐ役目を担っていることも、保険会社のひとつのビジネスモデルだと説明しました。
●いずれ来たる災害の発災時に、「被災が半分で安心が2倍」を実現するために
ディスカッションの最後では、モデレーターの原田教授が、防災技術のコアが発展していることを感じつつも、防災に対して本当に使えるようにするためは、技術が使いやすくなることや、それらが商用化もされていること、関連プレーヤー同士の適切な役割分担や枠組み作りが重要であると総括。そしてプラットフォーム学が重要している要素である「人を繋ぐ」、「データを繋ぐ」、最後は「専門を繋ぐ」ことが、今回のテーマであるデジタル防災においても、切り口として同様に重要であると議論を振り返りました。
議論から見えた今後の課題としては、発災時に耐えうる枠組みを作るための理想的な状況からは、まだギャップがあることを指摘。特に大手企業とベンチャー企業とでは文化や技術には大きな差があり、この差を埋めるためには、新たな「繋ぐプレーヤー」の参画が重要であるとのこと。また、この繋ぐプレーヤーが決して防災の専門家である必要はなく、生活者やデータなどを広い領域で扱い、それらを俯瞰的に見ている損害保険会社のような存在が適していることが示されました。
そしていずれ来たる災害の発生時には、「被災が半分で安心が2倍」をなんとしてでも実現することが大切であり、そのためには、様々な産学官プレーヤーが垣根を超えたコラボレーションをし続けることがいまできることであるとして、そのためにも、いざというときに「コミュニケーション不足でした」ということにならないように、今後もこういったセミナー等を継続していきたいと展望が語られて、セミナーは閉会しました。