report
2023.06.20
Vol.21『モビリティのエネルギーとプラットフォーム学』
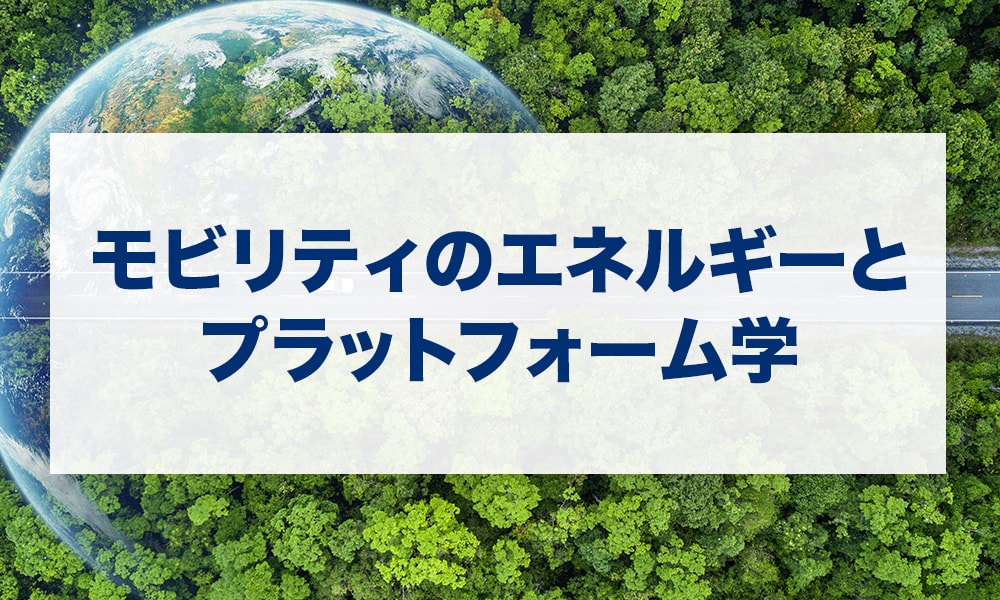
2023年6月20日に「プラットフォーム学連続セミナーVol.21 モビリティのエネルギーとプラットフォーム学 〜100年に一度の変革期を迎えた人・モノが移動するためのエネルギー〜」がオンラインで開催されました。EV(電気自動車)に30年関わった経験を持つ一般社団法人日本EVクラブの代表理事であり自動車評論家の舘内端氏と、ENECHANGE株式会社でEV充電サービス事業推進・情報発信を担当する田中喜之氏が登壇し、EV普及の鍵を握る「充電設備サービス」とモビリティとの関わり方について現状の解説やディスカッションが行われました。進行役は京都大学 プラットフォーム学卓越大学院 プログラムコーディネーターの原田博司教授が務めます。
●実は歴史が古いEVのこれまでと、現在進められている充電インフラの整備を俯瞰する
舘内氏からはまずEVと充電インフラについての解説がありました。EVは19世紀末に誕生し、特にアメリカでは20世紀に大量生産も始まっていました。しかし当時使われていたバッテリーは鉛酸電池で、現在使われているリチウムイオン電池に比べるとエネルギー密度はおよそ5分の1と非常に少ない電気しか蓄えられず、そのため航続距離も一度の充電で50~60km程度と短いものでした。そうしたEVからエンジン車に変わった大きな要因が、1901年にテキサスで油田が発見され、石油が大量に出たことで安価になったことが挙げられます。1913年にニューヨークからカリフォルニアまで約5000kmのハイウェイができると、航続距離が短く充電にも時間がかかるEVは安価なガソリンを入れるだけで長距離を走れるエンジン車に取って代わられました。
こうしてエンジン車が増えていった現在、二酸化炭素排出量の削減など様々な課題を解消するために、改めてEVに注目が集まっています。今後の展望について舘内氏は、EVまたは馬車しか走れないというスイスのある地域を例に挙げます。そこではEVを地元の小さい工場で作っているだけでなく、エネルギーも水力や風力、太陽光などで自給しています。つまり、これからの自動車は、必要な人が必要なものを必要なところで作っていくというような方に変わっていくのではないか。そうなった時に、充電のインフラはどう考えるのかが一つのポイントになると語りました。
前職の日産自動車から現職のENECHANGEまで、EV充電サービス事業を手掛けてきた田中氏から充電環境の現状についての解説が行われました。ENECHANGEは電力自由化に伴って電力会社を切り替えるサイトを立ち上げ、2015年に創業。電力会社が扱うデータを解析するというようなデータ事業に次いで、2年前から取り組み始めたのがEVの充電サービス事業です。2050年のカーボンゼロを実現するためには温室効果ガスを590億トン削減する必要があり、その効果が大きいのが電力網の脱炭素化と交通の電化です。
EV充電器は2014~2015年に政府から多額の補助金がついたこともあり、この2年間で非常に多くの充電器が設置されましたが、充電器の対応年数などの理由から、今年から来年に老朽化や契約終了で充電器が減少してしまう状況にあります。そこで同社では、EVを充電する3つのシーン:自宅や事業所などでの「基礎充電」、移動途中の「経路充電」、到着した場所での「目的地充電」それぞれに必要となる充電器の設置に取り組んでいます。現在はガソリンスタンドに行ってエネルギーの補充をしに行くというガソリン車の行動パターンが一般的ですが、EVの場合あらゆる場所に張り巡らされた電気をエネルギー源として、そこに充電器という蛇口を付けるだけで日本全国に置くことができるため、わざわざエネルギーを補給しに行くというガソリン車の行動パターンがなくなります。そこで同社では全国の宿泊施設や観光施設、ゴルフ場、大型ショッピングセンターといった滞在が長い施設への設置を進めています。利用者側のメリットとしては、欧州水準の充電器を設置しているため充電が早いことや、支払いを自動車メーカーでEVを買った際に契約する専用カードの他にアプリでも可能にしており、アプリでは充電スポットの場所や空き状況も確認できること。設置施設側のメリットとしては、補助金を活用することで費用の多くを賄うことが可能で、更に残りの費用もENECHANGEの補助により導入費用が0円になることや、補助金申請や設置工事の対応やアフターサポートなどがあるということです。
●EV普及の課題を考えることは、これからの移動や自動車の在り方を考えることでもある
後半のディスカッションパートは原田教授から舘内氏への、「1994年に日本EVクラブを立ち上げたとのことだが、なぜこの時期にEVに着目したのか」という質問から始まり、舘内氏は長年エンジン車に携わってきた中で1980年代から排出ガスによる健康被害を理由に「このままでは自動車は残れないな」という気持ちがあったとコメント。国際的にも問題視が進む中で、同時期に国立環境研究所・東京電力・東京R&Dなどが共同で開発したEV「IZA」に乗ったことで、「これなら自動車も生き残れるな」と感じ、日本でEVを広めようというのが日本EVクラブの発足の経緯だと語りました。
いっぽう最近のEVについて問われると「良くない方向に進んでいる懸念がある」と舘内氏は答えます。エンジン車が高性能・快適性を目指したことで巨大化し燃料消費量が増えたことが今の問題を作ったが、それと同じ轍をEVもまた踏んでいるのではないかと危惧している。再生可能エネルギーを使えば排出されるCO2はゼロになり、カーボンニュートラルにはなるが、自動車を作るエネルギーや材料もゼロにしなければならない。自動車はもっと小さく、スピードも下げないといけないのではないか、果たして今のEVの進歩の方向性がそのままでいいのか。世界中、特に欧州の都市では排出ガスの問題だけでなく、交通渋滞や交通事故などの問題によって生活空間が阻害されてしまうことも含めて自動車が問題視されているとし、「自動車はエネルギー変換だけの変革が求められているのではない」との考えを述べました。
これを受けて田中氏は「日本と欧州には格段の差がある」と語ります。急速充電器はそれほど変わらないが、普通充電器の数が圧倒的に違う。その理由の一つはEVの普及率で、新車販売におけるEVの割合が日本は3~4%に対して欧州は10%を超えている。それに伴って市民の意識というのも大きく違うのではないかと思うと述べました。原田教授が、EVが増えると充電ステーションが増える、充電ステーションが増えればEVが増えるというニワトリと卵の問題なのではないかと疑問を呈すると舘内氏は、アメリカで5000kmの大横断道路ができたのが自動車発展の鍵だったように、日本では田中角栄元首相の所得倍増計画の鍵になっていたのは道路インフラの整備建設拡大だと思うと発言。道路ができた→車が増える→車が増えるから道路が増えるという上昇拡大方向に働いたのを考えると、EVが増える→充電施設が増える→EVが増えるというのは自然の成り行きではないか。1回の充電で300km走れるEVも増えてきており急速充電器による途中充電はそこまで重要視されなくなってきたが、普通充電器による基礎充電・目的地充電はまだ充実していない。これをもっと普及して観光地に行けば絶対充電できるということが普通になってくると好ましいと語りました。田中氏は基礎充電に関してはマンションの動きが活発化していると言います。3、4年前は提案してもマンションの管理組合で合意形成が得られなかったが、昨年から今年にかけてEVの普及が進み、また東京都がマンション充電設備普及促進に向けた連携協議会を立ち上げるなど、充電設備がマンションの価値を上げるということもあり、最近は住民の方々の一定数の理解を得られるようになった。合意形成を得るのに時間はかかるが、2、3年後に花が咲いてくる時期があるのではないかと思う、との意見を示しました。
EV普及の技術的課題について問われた田中氏は「動力系とICT系の2つに分かれる」と答えます。動力系についてはバッテリーやモーターなどプレイヤーも増えて競争も激しくなっており進化を続けているとしつつ、ICT系について特に課題となっているのが統一されたプラットフォームがないこと。自動車の内部はCAN(Controller Area Network)という統一した規格になっているが、そこからサーバーに情報を上げる部分は各メーカーがそれぞれプロトコルを作っている。この上位のプラットフォームを誰がどういうふうに運営していくかというところが一つの課題であり、願わくばサーバーのその上のレイヤーで各社の施策が合ってくるとさらに活用方法が広がるだろうと、現状の課題と今後の展望について語りました。また、データの流通基盤が整備されておらず、データの所有権や知財権を国が主導してまとめていくことが必要ではないかとも指摘。急速充電器はCANという車の規格を使っているため双方向通信がやりやすいが、普通充電器は通信のシステムが比較的簡易に作られているため、車の情報は車から、充電器の情報は充電器から取得しなければならず、知財の問題とシステムの問題、両面からアプローチして活用していくと少し時間はかかりそうだと印象を語ります。また舘内氏はEV普及の遅れから充電規格の面でも世界標準を日本が握れなかったことを踏まえ、EVに関してのルール形成にも「日本は積極的に関わっていかないといけないと思う」と述べました。
セミナーを振り返り舘内氏は「ガソリン車でなくなるということはなぜなのか、多くの人にもっともっと考えていただきたい」と言います。確かに環境問題とエネルギー問題がきっかけだが、もっと言えば自動車を使った交通そのものを考えていかなければならない時代に入っているとして、自動車という移動の道具を我々はどう扱っていくのか、現状の自動車の在り方自体に課題はないか、自動車産業に従事する方々を中心にもっと検討していかなければならないと今後の展望に対する提言を示しました。