report
2023.11.30
Vol.25『多様化する学びとプラットフォーム学』
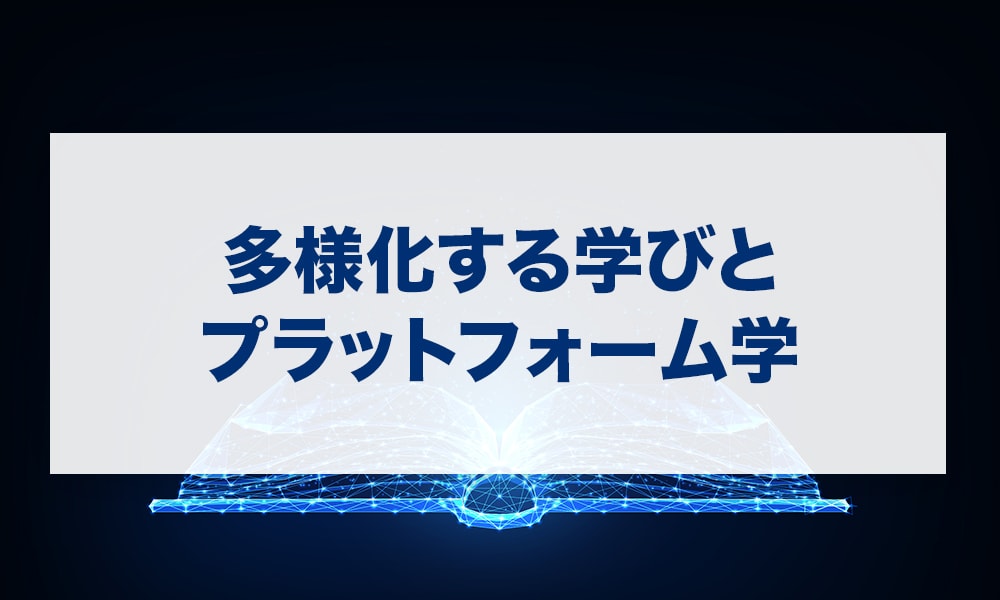
2023年11月30日に「プラットフォーム学連続セミナーVol.25「『多様化する学びとプラットフォーム学』~学び方の選択肢を増やすデジタル戦略とは~」が会場とオンラインにて開催されました。
リクルートの池田脩太郎氏、角川ドワンゴ学園の出雲路敬行氏が登壇し、両社の事業を通じて現在の学びの最前線を解説するとともに、多様化する学びの未来についてディスカッションが行われました。進行役は京都大学 プラットフォーム学卓越大学院 プログラムコーディネーターの原田博司教授が務めています。
●オンライン教育の普及で広がる学びの形態
冒頭はリクルートの池田氏による、オンライン学習サービス「スタディサプリ」の解説から始まりました。2012年に大学受験生向けの「受験サプリ」として始まり、その後高校生全学年向けのB2C、小中高校の先生向けのB2B、社会人向けの英語学習、そして海外の展開という形で事業を拡大。現在はB2Cよりも学校向けのB2B事業のシェアが高まっており、日本におよそ5000校ある高校のうち、2000校以上で導入されている実績があります。
サービス開始から約10年、スタディサプリは3つの要点を軸に提供価値をアップデートしてきました。①良質なコンテンツ:講義動画の視聴率の推移から生徒の離脱ポイントを分析。冒頭の授業の目的を本編から切り離したり、考える時間をカットしたりして、講義動画の満足度のレーティングを上げるよう改善しています。②個別最適な学習体験:自分が分からなかった苦手を明らかにして次に学ぶ講義動画をレコメンドするアダプティブ学習は、分かる人と分からない人を二極化させていく構造にあります。これを解決するために、苦手を克服するための概念理解を中心とした講義動画に力を入れいています。③継続しやすい仕組み:生徒が学習で孤立しないように、先生や大学生のコーチに伴走者になってもらいます。コーチングで効果が高いのは質問対応よりもモチベーションサポートで、スタディサプリを導入している学校では生徒よりも先生に継続してプロダクトを使ってもらうことを重要視しています。
続いて角川ドワンゴ学園でPBL教材(問題解決型学習の教材)の制作を担当する出雲路氏が、、N高等学校・S高等学校(N高・S高)について解説を行いました。ネットと通信制高校の制度を活用した“ネットの高校”として、2016年に設立されたN高(沖縄県)と2021年に設立されたS高(茨城県)。両校は本校の場所以外には違いがなく、大きく分けるとネットコースと通学コース、オンライン通学コースの3つのコースがあります。ネットコースは自分の自由な時間、自由な場所で学習を進めていくスタイル、通学コースは全国69カ所にあるキャンパスに通うスタイル、オンライン通学コースはネット上のオンライン教室に通うスタイルと、多様な生徒を受け入れるスタイルを目指しています。総生徒数は2万6197人(2023年9月30日時点)で、他にもプログレッシブスクールのN中等部、日本財団と連携して2025年に開学予定のZEN大学(仮称、設置認可申請中)があります。
N高の特色はICTツールを駆使して、自由な時間・好きな場所で学習ができることです。そうして増えた時間で自分のやりたいこと、将来へつながる多くの経験ができるとしています。通学コースでは、自分がやりたいどの方向に行っても活躍するために、正解のない問題に取り組むスキルを学習する21世紀型スキル学習や社会の問題発見と課題解決を実践するPBLなどの学習プログラムを用意しています。他にもプログラミングや大学受験用のオリジナルの課外授業、各界の著名人・トップランナーを招いた特別授業、起業部や投資部などのネット部活も用意されています。「多様な生徒の多様な生き方の芽を摘まない」という考えのもと、やりたいことがある子供の受け皿になったり、いろいろなコースやプログラムを用意して家庭や生徒それぞれに合った学びの形を提供することを目指しています。
●新技術で変わる学びの形態。教育現場の改革は生成AIにアリ?
後半のディスカッションパートは、スタディサプリが生徒個別のB2Cから学校全体のB2Bに変わったきっかけについての質問で始まりました。池田氏は、B2CのスタディサプリのCMを見た高校の先生からの問い合わせがきっかけだと答えます。日本の先生の労働時間は社会問題になるほど増えていて、生徒の実績を出すには補修が必要だが補修をすればするほど先生の人件費が上がってしまう。スタディサプリを導入すれば補修時間を減らすとともに学校の実績にもつながるのではないかという話を聞いて、100校くらいにリサーチしてみたらニーズがあった。そういったn=1の偶然の産物からB2B事業が始まった、と当時を思い返しました。
N高の認知度が急激に上がったきっかけや技術的要因について問われた出雲寺氏は、コロナ禍によってリアルな学校が閉鎖する中、オンラインのN高だけは学びが止まらなかったところから火が付いた。もともとドワンゴはIT企業でもあったため技術的要因は少なく、コロナや世の中が多様化するといった社会変化の方が要因としては大きかった、と見解を述べました。
YouTube等で無料の教育コンテンツが提供されていることについて、池田氏はユーザーが学びの機会を得る接点が増えるので歓迎していると答えます。ただ、スタディサプリが始まった10年前から無料の学習コンテンツを提供しているプレーヤーはいたが、現在も継続している人はほとんどいない。YouTubeの場合、スポット的に学ぶのには向いているが、体系的に学ぶのには適していなかったり、無料だとコンテンツが磨かれずに劣化していくので学ぶ人が離れていくというジレンマに陥ってしまうと分析します。出雲寺氏も池田氏の見解に賛成したうえで、生徒にYouTubeで学習することを止めるつもりはなく、YouTubeがいいと思ったらYouTubeで学んでほしいと思っていると述べました。
N高やスタディサプリをもっと広げていくうえで一番の障害となるものは何かという問いに対して出雲寺氏は、PBL教材をつくる立場でと前置きをしたうえで、現在通学コースに通う約8000人の生徒には基本的には同一の教材を提供している。これからさらに増えていくのに加え、多様化する学びを支えるためには同一の教材で果たして有効なのか。もし生徒層に合わせた教材を用意するとなると人的リソースが全く足りなくなる、との見解を示しました。池田氏は提供するセグメント(学生/社会人)によって変わると説明。近い将来、ほとんどの学生はスタディサプリ含むオンライン教育を使うことが当たり前になり、企業が提供するサービスをどう磨いていくが論点になる。一方、社会人はオンラインを含めて学ぶ環境をどう作るかがボトルネックになっている。日本の社会人は仕事が忙しいから学ばないと言われていたが、コロナ禍で可処分時間は増えたけど学習時間は増えなかった。学ぶことがその先のキャリアアップに明確につながっていない社会構造が原因だろう、と分析しました。
ICTが発達することによる教育現場のデメリットについて問われた池田氏は、あまりデメリットに出合ったことがないと答えます。学校現場に導入するときに、リアルの先生の授業を聞かなくなるのではと言われることが多いが、実際はあまり起きてなくて、むしろ授業が終わった後に質問しにくる生徒が増えたとも聞く。また、英語の授業で文法はスタディサプリに任せて、リアルの授業は英会話の授業に変えているなどメリットの方が多いと思う、と述べました。出雲寺氏は教員、保護者、生徒のリテラシーの差を挙げました。例えばChatGPTのような新しい技術が出てきた場合、ある程度ルール整備が必要になるが、リテラシーに差異がある状態で確立するのは時間がかかる。今後も新しい技術が出るたびにそういった対応するのにかかるコストがデメリットと言えるかもしれない、との考えを示しました。
注目している新しい技術について、池田氏は生成AIは今後4、5年は外せないテーマになると回答。講義動画を作るには、問題をつくる人、講義をする先生、動画を撮影する人、編集をする人とそれなりにお金がかかる。生成AIを使えば今でも小学生くらいの問題はつくれるし、内部で試しているがコストは9割くらいカットできたり、制作時間も半分くらいになる。生成AIの利用は加速度的に止められなくなるし、現場の先生方にはぜひ使ってほしい。我々がやっていることをそのままやるだけでも、日々の授業準備や評価付けなどの作業が劇的に軽くなる、と今後のAI利活用について語りました。
出雲寺氏も、AIを利活用することで究極的には先生は何も教えず、生徒が自主的に学べて、先生は伴走者として生徒を支えるのが理想だと述べました。また出雲寺氏は注目する技術としてメタバースも上げました。学びの中でリアルとオンラインの間に位置するのがメタバースであり、実際は遠くにいてもメタバース上でアバターになって同じ世界観にいると疑似的に本当にここにいるような感覚になる。N高でもメタバース教育を進めているがまだ足りていない部分があるが未来がどうなるかは気になるところだ、と展望を述べました。
最後に日本オリジナルのプラットフォームは何になるかという質問に対して池田氏は、どのインダストリー、どのビジネスモデルでやるのかで変わってくる。現在世界最大のプラットフォームの一つはGoogleだが、過去にはリクルートと競合するHR領域に入ってきたこともあるがすでに撤退している。YouTubeももっているので、スタディサプリのようなこともやろうと思えばできるがやらない理由はGoogleのマネタイズの9割が広告だからだ。広告のユーザーをどれだけ最大化するかに投資のリソースが配分される構造になっていて、検索は一つのプラットフォームで全世界をカバーできる。教育コンテンツは各国ごとにローカライズする必要があるが、そのやり方はGoogle内では優先順位が上がらない構造になっている。戦う相手が構造的にやってこない領域で勝負をするという考え方はあると思う、と語りました。